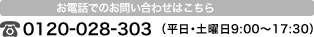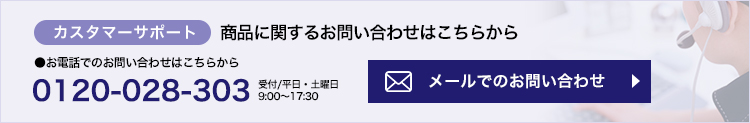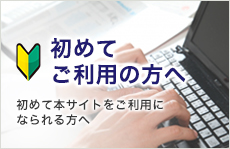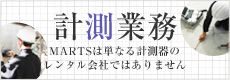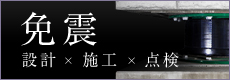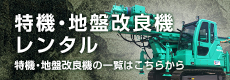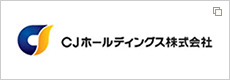コンクリート製品や構造物の検証に欠かせない「非破壊検査」を解説

コンクリートでできた構造物は非常に堅牢につくられていますが、屋外で雨風やその他の自然にさらされると少しずつ劣化していきます。そこで、トラブルの早期発見・早期対処に「非破壊検査」が行われます。
非破壊検査は、対象の構造物を壊すことなくコンクリートの劣化具合を把握し、傷や欠陥を把握できる方法です。検査によって構造物の品質が把握できるため、建物の所有者にとっては保有資産の正確な状態把握にも役立ちます。
この記事では、コンクリートの非破壊検査の概要や目的、メリットとデメリットを紹介します。検査の種類や注意点もぜひ参考にしてください。
コンクリートの非破壊検査とは
コンクリートの非破壊検査とは、コンクリートでできた構造物が基準を満たして建造されているかを把握し、傷や劣化がどの程度あるかを知るための方法です。
目視だけではわかりにくい内部の損傷が調査できるため、ビルやコンクリートでできた橋・トンネルなどの構造物の経年劣化を調査する際に用いられています。
非破壊検査は、初期点検や日常点検といった点検のうち、定期点検・臨時点検・緊急点検の際に行われます。点検の種類と検査方法は次のとおりです。
【点検の種類と方法】
| 点検の種類 | 点検の目的 | 点検方法 |
| 初期点検 | 維持管理開始時に初期状態を把握する |
|
| 日常点検 | 日常的に、構造物の状態変化を把握する |
|
| 定期点検 | 1年ごとまたは数年に1度、構造物の状態をより広範囲に把握する点検 |
|
| 臨時点検 | 外力(地震、衝突)で損傷した構造物の点検 |
|
| 緊急点検 | 損傷構造物(事故が生じた構造物)と類似の構造物への点検 | 外観調査(目視、写真、双眼鏡)たたき調査非破壊試験 |
国土交通省では、2006年度より新設する一定規模の構造物に対して、非破壊検査による構造物中の配筋状やかぶりの状態測定を実施しています。また、2007年度からは同じく非破壊検査による圧縮強度測定を行っています。※
※参考元:国土交通省「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定試行要領(案) 」
コンクリートの非破壊検査を行う目的
非破壊検査の目的は、構造物の安全性や品質の確保、事故トラブルの防止などが挙げられます。
【コンクリート非破壊検査の目的】
- 構造物の強度が確保されているか確認するため
- 構造物内の劣化・欠陥の程度を確認するため
- 安全性の確保・不慮の事故やトラブルの防止
- 欠陥トラブルによる金銭・人的コストの削減
橋脚やトンネルのように多くの人に利用され、一定以上の大きさや重さをもつ構造物は、安全性を確保しなければならない構造物に対しては、定期的な検査が欠かせません。
そのような対象に対して、非破壊検査は部分または全体を破壊せずに内部の状態を確認できる方法です。
非破壊検査で劣化の程度を確認し、損傷が甚大であれば修繕や建て直しが行えるため、トラブルが起きる前にすばやく対応できます。
非破壊検査のメリット
非破壊検査は対象を壊すことなく、安全かつ価値を損なわない状態で検査ができるため、資源を無駄にせず環境にもやさしい検査手法です。
トンネルや橋のような公共物は、一度破壊してしまうと修復するまで使用できなくなるため、地域全体に影響が及んでしまいます。
一方、非破壊検査は再建築までの負担がかからず、構造物を運用しながら劣化の程度を調査できます。
コンクリート構造物の劣化が進むと、崩落や崩壊によって重大な被害が出るおそれがあります。外見だけではなく内部にもひび割れが発生するため、目視だけではわからない劣化を非破壊検査によって確認できると、重大な欠陥が事前に発見できる可能性があります。
建造したばかりの構造物でも、安全に造られているかを確認するために非破壊検査が行われる場合があります。また、将来的な劣化の予測や残存寿命の推定にも活用されています。
非破壊検査のデメリット
非破壊検査では電磁波レーダーを使って伝播速度を測定したり、超音波を当てて構造物内の伝播速度から欠陥やひび割れの深さ等を調べたりします。
検査手法によっては準備にコストや時間がかかり、装置の取り扱いについて労働安全衛生法の規定に準じる必要があります。検査を行う際、担当者は法律やその他のルールを熟知し、現場の環境や安全にも配慮しながら実施しなければなりません。
また、非破壊検査は外側から行う検査です。劣化や損傷が目視で確認できるのは表面や外側のみで、破壊しなければ直接目視による検査ができない点がデメリットといえるでしょう。
関連記事:超音波流量計とは?原理・特徴・メリットと超音波以外の流量計を紹介
コンクリートの非破壊検査の主な種類
コンクリートの非破壊検査にはさまざまな手法があります。
目視による試験やCCDカメラによる間接目視試験、フィルムに対象の構造物の表面を写して顕微鏡で検査するスンプ法試験などが行われていますが、より詳細な方法として電磁波レーダー法や電気化学的方法も実施されています。
反発度やファイバースコープなど、それぞれの検査方法と手順を確認していきましょう。
反発度に基づく方法
反発度法とは、コンクリートの強度を確認するための調査方法です。
測定対象となる構造物の表面を「リバウンドハンマー」と呼ばれる物で打撃し、反発の程度から圧縮強度を算出します。
コンクリートの乾湿に左右されやすく、部材厚の小さな部分を打撃しないように注意する必要がありますが、曲面でも平面との差が少なく、測定者の熟練度にも依存しないため、比較的手軽にできる検査方法といえます。
電磁誘導を利用する方法
電磁誘導法とは、コイルに交流電流を流して磁界を発生させ、その中に対象物を配置して鉄筋の位置やかぶりを測定する方法です。
磁界の作用によって渦電流が発生しますが、傷があると渦電流が乱れるため、傷のある場所の検知も行えます。
コンクリートと鉄筋の性質の差を利用するため、非破壊での検査が行えます。コンクリートの湿潤や品質に左右されず、表面の影響も受けないため、鉄筋の位置や鉄筋径の推測に適しています。
弾性波を利用する方法
弾性波法とは、コンクリートの面を打撃して弾性波と呼ばれる内部の波形を振動センサーで受信・測定し、コンクリートの厚さや状態を調べる方法です。
コンクリートの品質や浮きを調べる「打音法」圧縮強度や品質を調べる「超音波法」欠陥や内部の部材寸法を調べる「衝撃弾性波法」といった種類があります。
衝撃弾性波法は比較的大きな構造物にも適用できることから、トンネル点検などにも用いられています。
関連記事:構造物の振動を計る「振動計」の仕組みと目的・測定の重要性
電磁波を利用する方法
電磁波レーダー法は、電磁波を放射する機器を使ってコンクリート表面に電磁波を当て、構造物の内部を調べる方法です。
電磁波はコンクリートをまっすぐ進みますが、鉄筋や塩ビ管といった電気的性質が異なる素材に当たると反射するため、内部の状態が推測できます。
電磁波は危険性が低く、構造物を壊すことなく電線や鉄筋といった部材の位置を探査し、空洞やひび割れの状況を調査することができます。
電気化学的方法
電気化学的計測法は、電気を利用してコンクリート内部の状態や寸法を推測する手法です。
コンクリート内の鋼材に腐食が起きていないかを調べる「自然電位法」「分極抵抗法(交流インピーダンス法)」は、どちらも鋼材の一部を取り出す必要があり、微破壊調査として利用されてきました。
地面に人為的に電気を流して電位差を測定解析し、構造を把握する「四電極法」という方法もあります。この方法ではコンクリートに電極を差し込んで電気抵抗値から状態を調べることができます。
ファイバースコープを用いる方法
非破壊検査用ファイバースコープは、埋設された金属・非金属を探知する工業用の内視鏡です。
ファイバースコープを使用すると、X線検査で探知しづらい埋設管の診断や、配管内のサビ・劣化を高精度に把握し、耐用年数の推定も行えます。コンクリート構造物の目地・基礎の接合部のような細かい箇所の状態も調査できます。
事前に電磁波レーダー法や弾性波法によって問題が起きている箇所を確認しておけば、ファイバースコープでその部分に絞り込んで詳細を確認できます。
スコープには音声マイクやカメラが搭載され、モニターを通じて音や画像を映し出して記録できます。あとからそれらの情報を確認し分析すれば、より詳細な非破壊検査が行えます。
コンクリートの非破壊検査を行う際の注意点
コンクリートの非破壊検査を行う際に注意したい3つのポイントを確認していきましょう。
検査のための許可を取得する
非破壊検査の際には、建造物の所有者や建造物のある場所の管理者に許可をとる必要があります。
はじめに、検査の目的や手法、検査の意義と検査範囲を把握し、検査対象に適した手法と機器を選定します。そのプロセスを終えてから、法令や規則に従って手続きを行い、確認と許可を得て検査を実施します。
また、非破壊検査を行う際には専門的な知識や技術が求められます。無資格では検査が認められない可能性がありますので、有資格者に検査を依頼するか、専門の資格認証を受けてから検査を実施してください。
検査を行う範囲を正確に把握する
検査の対象となる構造物が一定以上の大きさになる場合、範囲を決めてから測定を行いましょう。
検査範囲を確定するためには、コンクリートの厚みや凹凸、詳細な材質や内部の状況、経年劣化・使用状況を考慮します。範囲を絞り込むことで検査精度が高まり、指定した範囲に適した検査方法を選びやすくなります。
機器によっては測定に適していない(精度が落ちてしまう)場合があります。検査範囲に適した測定機器を選定し、種類や性能も考慮しておきましょう。
正確な測定を行う
非破壊検査を行ったあとは、測定結果報告書と呼ばれる報告書を作成し提出します。
国土交通省が所管する国土技術政策総合研究所では、「非破壊検査技術の性能評価試験法で用いる様式 (案)」として検査対象の内容や検査者の氏名、計測方法や判定方法に関する手順・手法をまとめるための様式案を公開しています。※
※参考元:国土技術政策総合研究所「非破壊検査技術の性能評価試験法で用いる様式(案)」
コンクリート非破壊検査の手法や利点をチェック
今回は、非破壊検査の概要とメリット・デメリット、注意点について紹介しました。
非破壊検査は、コンクリートでできた構造物や製品の品質を確認し、安全を確保するために重要な手法です。
測定機器の精度向上や検査手法のバリエーションが増えたことから、従来の目視点検や打法で確認できなかった詳細な劣化や欠陥も把握できるようになりました。
メリットだけではなくデメリットもありますが、長期的にコンクリート構造物を使用する場合は有意義な作業といえるでしょう。