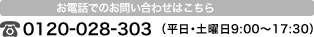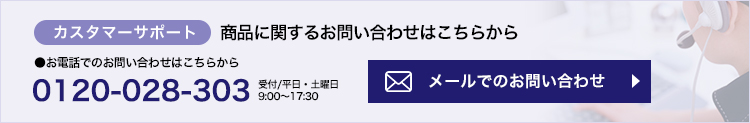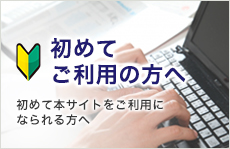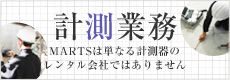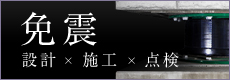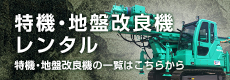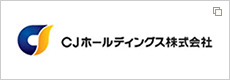環境測定や設備管理に使われる「風速計」の使用用途と動作原理

風速計は、屋内外に吹く風の速さを測る機器です。工事現場や建設現場では環境測定などのために風速測定が求められ、作業環境を整えるために重要な役割を果たしています。
風の流れが少ない屋内でも、空調設備の設置やメンテナンスに風速の測定が必須となるため、風速計の使用が必要です。
この記事では、風速計の使用用途・種類・動作原理・使い方を紹介します。
風速計使用時の注意点についても取り上げていますので、計測機器選びの参考にしてください。
風速計とは?
風速計は、プロペラ部で風を受けて信号に変換し、解析後に数字として表示する計測機器です。
「風向風速計」として、速さのほかに風の向きも計測できるものもあります。
手に持ったまま使える簡易的な機器から、管区気象台に設置されている大型の装置まで、さまざまな形状・機能・サイズが揃っています。
一般のユーザーにも選ばれる簡易型や小型のほか、高性能な計測結果が得られるデジタル型もあります。
風速計の使用用途
風速計は次のような使用用途に用いられます。
【風速計の使用用途】
- 安全管理
- 環境測定
- 気象観測
- 災害対策
- 安全規則準拠のため
- 設備の検査・メンテナンス
- 屋内外のイベントやスポーツ前の計測
工事や建設現場の安全管理、風による影響を受ける可能性のある作業・イベントの実施前には、風速を測定して活動や作業に適しているかを判断します。
強風が吹いているときには作業や活動に加えて飛行機やヘリコプターの運行にも影響するため、風速計は安全管理に欠かせないものです。
気象観測にも風速は欠かせない要素です。風の動きと強さを計測し、気温や湿度といった他の要素と組み合わせることで、天気予報に活用されています。
屋内においても、空調設備の検査やメンテナンスに使用されています。
有害な空気を排出する工場の換気システムを正常に動作させる際に、十分な風量が得られているかを計測するために風速計が使われます。
風速計の種類と動作原理
風速計の種類は、風車式・熱式・風杯型・風向風速計・超音波式といった種類があります。
すべて同じ風速を計測する計測機器ですが、計測のための特徴が異なっています。5つの風速計の特徴をみていきましょう。
風車式風速計
風車式風速計(ベーン式風速計)は、風車のような形のプロペラ部が設置され、そこで風を受け止めて回転した回数で風速を測定する機器です。
手で持って使えるハンディタイプのほかに、気象庁の管区気象台が設置している風見付きの風速計にも風車式が採用されています。
小型のタイプはハンディ扇風機のような形状で、手で持った状態のまま風速が計れるため、事務所や事業所、屋内外での簡易的な測定に適しています。
熱式風速計
熱式風速計は、風を受けると温度が下がる「抵抗体(プローブ)」を組み込んだものです。
風を受けて抵抗体の温度が上下すると電気抵抗の値が変化し、その変化の程度を風速に換算して値を表示する仕組みです。
抵抗体は風の影響で温度を変えるため、屋内外の温度変化が激しい場所では正確な測定値が得られない可能性があります。そのため、温度変化が少ない室内での測定に適しています。
環境の温度変化が少ない場所なら、狭い場所でも測定しやすいため場所を選びにくいメリットがあります。
風杯型風速計
風杯型風速計とは、風杯と呼ばれるカップ状の部品が取り付けられた風速計です。
風杯が風を受け止めると回転し、回転数を変換して値を計算します。
屋外のように風が吹き付ける場所では精度が高くなりますが、狭い場所ではほとんど風を受けられないため、屋外の作業現場や高所、クレーンの上部に取り付けて使われています。
カップ部を防水タイプにすれば天候に左右されにくく、ほとんどすべての気象条件に適応します。
風向風速計
風向風速計は、風の吹く速さ(風速)と風向き(風向)を計測できる計測機器です。
風速だけではなく風の向きも知りたいときに使われ、気流の状況や天気の変化を予測する際にも活用されています。
気象庁では大型の風向風速計を鉄塔の上に設置し、胴体と尾翼でそれぞれ風を受けて風向きを、プロペラが回る回数で風速を測定する「風車型風向風速計」を気象観測に使用しています。※
※参考元:気象庁「風向風速計」
超音波式風速計
超音波式風速計は、トランスデューサーと呼ばれる変換器を用いて、発信部と受診部を向かい合わせに設置し、その間に風を通すことで風向と風速を測定する計器です。
発信部と受診部の間には超音波が流れており、風が通ると発信から受診までの到達時間が変化します。その時間変化から風速を計測できる仕組みです。
屋外では建築現場や土木工事現場の安全管理に使われ、屋内では製造工場やクリーンルームでも活用されています。
関連記事:超音波流量計とは?原理・特徴・メリットと超音波以外の流量計を紹介
風速計の使い方
風速計にはいくつかの種類があり、風車式・熱式・風杯型の3種類が一般的に使用されています。
それぞれの使い方を詳しくみていきましょう。
風車式風速計の場合
風車式風速計は、プロペラで風を受けて風速を計測します。
風をしっかりと受けられなければ速度が求められないため、風の吹く方向と垂直になる方向(風速がもっとも大きくなる方向)にプロペラを向けて測定します。
プロペラの方向がずれると風を半端に受けたり、正しく回転しなかったりするため、風向を考慮して正しい位置で測定するようにしてください。
熱式風速計の場合
熱式風速計は、測定したいところに抵抗体を近づけて測定します。
抵抗体には指向性があるため、抵抗体を風の方向に向けて表示される値を確認し、最大になる部分で計測を行いましょう。
熱式は周囲の風温に左右されやすい計測機器です。
温度補償機能を搭載していないものは風温との温度差が保てないため、風による影響と温度変化に注意が必要です。
風杯型風速計の場合
風杯式風速計はカップを回して風速を調べます。
カップの回転方向と風の吹く方向を揃え、風の吹く方向とカップの回転軸が垂直になるように調節してください。
他の風速計と同様、風速の表示がもっとも大きくなるところに向きを調整し、測定を行いましょう。
風速計を使用する際の注意点
風速計はいずれも測定したい風を受け止められる場所で測定を行う必要があります。
測定の注意点は次のとおりです。
【風速計の使用上の注意点】
- 設置場所や測定場所を調整する
- 障害物や遮蔽物がない場所を選ぶ
- 屋根の上は側面を避けて設置する
- 汚れや詰まりを取り除いておく
風速計の計測または設置場所は、土台が安定した場所や測定者が安全かつ不安定にならない場所を選びましょう。
風速計の近くに障害物や遮蔽物がないところ、または障害物や遮蔽物がある場合はできるかぎりそこから離した場所で測定してください。
屋根の上などに設置するときは、特定の方向からの影響を避けるために屋根の側面や端は避け、中央に設置してください。
使用目的に合わせて風速計を選ぶ
今回は、風速計の使用用途・種類・動作原理・使い方について紹介しました。
風速計は、屋内外の工事や建設現場、航空機・列車・船舶などの運行、空調設備やイベント開催の可否を調べるために、幅広い用途で使われています。
風車式・熱式・風杯型・風向風速計・超音波式と複数の種類がありますので、測定方法や計測の目的に応じた機器を選びましょう。